人生とは「苦」を背負って生きていく道
無常とは
無常とは無常とは虚無ではなく、物事が成長するプラスの面を見ること四苦八苦は人間が生きていくうえで付いてまわるとブッダはいいました。
そしてさらに「無常に基づく苦」があると。
無常というと日本人は『平家物語』の冒頭にある「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり」を思い出します。
「人生の短いことをはかなむ」といった意味でとられがちですが、仏教の経典に出てくる「無常」は少し意味が違うようです。
無常というのはブッダの教えそのものですけれど、日本では今、非常にセンチメンタルでマイナス的なものとして、とらえられていました。
これは無常を感情や情緒として感受するためです。
感情的にとらえると、どうしても虚無的になりやすいのですが、それはいうなれば「無常感」といったものです。
ブッダの説く無常はそうではなくて「無常観」。
すべて存在するものは絶えず移り変わっていると観察する人生観であり世界観です。
経典では、人間が「生あるものは必ず死ぬ」という赤裸々な事実や現実をそのまま受け入れたとき、そこにある種の深い感動が生まれ、そこから感嘆がわき出てきます。
それが「無常」だといっています。
つまり、「無常に基づく苦」というのは「生あるものは必ず死ぬ」という事実そのものを指しているといっていいでしょうか。
その事実を受け入れて、なおかつ前向きに生きていこうということでしょう。
ブッダが成道して悟った時、衆生の多くは人間世界のこの世が、無常であるのに常と見て、苦に満ちているのに楽と考え、人間本位の自我は無我であるのに我があると考え、不浄なものを浄らかだと見なしていた。これを四顛倒(してんどう=さかさまな見方)という。
この「無常」を説明するのに、「刹那無常」(念念無常)と「相続無常」の二つの説明の仕方がある。刹那無常とは、現象は一刹那一瞬に生滅すると言う姿を指し、相続無常とは、人が死んだり、草木が枯れたり、水が蒸発したりするような生滅の過程の姿を見る場合を指して言うと、説明されている。
この無常については、「諸行無常」として三法印・四法印の筆頭に上げられて、仏教の根本的な考え方であるとされている。
なお大乗仏教では、世間の衆生が「常」であると見るのを、まず否定し「無常」であるとしてから、仏や涅槃こそ真実の「常住」であると説いた。これを常楽我浄と言うが、これについては大乗の大般涅槃経に詳しい。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本人と「無常」
「祇園精舎の鐘の声」で始まる軍記物語『平家物語』、吉田兼好の随筆『徒然草』、「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」で始まる鴨長明の『方丈記』など、仏教的無常観を抜きに日本の中世文学を語ることはできません。
単に「花」と言えばサクラのことであり、今なお日本人が桜を愛してやまないのは、そこに常なき様、すなわち無常を感じるからとされています。
「永遠なるもの」を追求し、そこに美を感じ取る西洋人の姿勢に対し、日本人の多くは移ろいゆくものにこそ美を感じる傾向を根強く持っているとされています。
「無常」「無常観」は、中世以来長い間培ってきた日本人の美意識の特徴の一つと言って良いでしょう。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

「四諦」
人生の根本にある真理を「四諦」という、四苦八苦を背負いつつ、この世は無常であるという真実から目を反らさずに、なおかつ希望を持って明るく人間らしく生きていこうと。
そういう道があるか、とブッダは自らに問うたわけです。
そして、「ある」と考えました。
それから次に、「ある」とすればどうしたらそれを実現できるのかと考えるわけです。
そして語られたのが「四諦」という四つの真理です。
その四つとは
「苦しみ」
「苦しみの起こるもと」
「苦しみを減らし、なくすこと」
「苦しみを減らし、なくした状態に導く道」
* 苦は「知り尽くすべきもの」(遍知)
* 苦の原因は「滅するべきもの」(滅除)
* 苦の滅は「実現すべきもの」(成就)
* 苦の滅を実現する道は「実践すべきもの」(修習)
というものです。
これを解釈しますと、まず大切なのは真実の生き方とは苦を背負いつつ生きていく道であるという確信を得ることである。
次に、そういう真実の人生を生きようとする人間の努力を妨げているもとになるのは煩悩です。
この煩悩をコントロールして、もっと澄んだ心持ちになっていけば、「苦」の世界を活き活きと人間らしく生きて行けるはずです。
そのための道を指し示しかものが仏道だ、と。
その四つを、「苦節」「集諦」「滅諦」「道節」といいました。
「諦」はあきらめでなく、「真理」です。
この四つが人生の根本にある真理だと釈尊は教えたのです。
それを知ることは決して虚無に陥ることではなく、むしろ、よりよく生きる道が開けるということなのです。
釈尊は確かに「この世は苦である」といいましたが、亡くなる前には「この世は美しい。人間の命は甘美なものだ。」といっていました。
これは「苦であるがゆえに、そこに美しいものが生まれてくる」という釈尊のひとつの悟りであったよう思われます。
ブッダは何をいいたかったのでしょうか。
現実には素晴らしいものはたくさんあるし、美しいものもたくさんあります。
しかし、それらはあっという間に過ぎ去り、消えて失われていくものです。
自分も同じく、やがて死んでいくものです。
ブッダが町や木を見て「楽しい」「美しい」といったのは、苦の世界において生を肯定している言葉だと思います。
「この世は美しい。人間の命は甘美なものだ。」というのもそういうことです。
しかし、この世という全体は「苦」なのです。
そうした苦の世界をどのように生きるかなのです。
そこから人間の煩悩を断ち切って苦しい人生をよりよく生きるという実践論が出てくるわけです。
四つの真理
苦諦
苦諦(くたい、duHkha-aaryasatya)とは人生の厳かな真相、現実を示す。「人生が苦である」ということは、仏陀の人生観の根本であると同時に、これこそ人間の生存自身のもつ必然的姿である。このような人間苦を示すために、仏教では四苦八苦を説く。
四苦とは、生・老・病・死の4つである。これに、
* 愛する対象と別れねばならない「愛別離苦」(あいべつりく)
* 憎む対象に出会わなければならない「怨憎会苦」(おんぞうえく)
* 求めても得られない「求不得苦」(ぐふとっく)
* 最後に人間生存自身の苦を示す「五陰盛苦」(ごおんじょうく)、または「五取薀苦」(ごしゅうんく)
を加えて「八苦」と言う。非常に大きな苦しみ、苦闘するさまを表す慣用句「四苦八苦」はここから来ている。
集諦
集諦(じったい、duHkha-samudaya-aaryasatya)とは、苦が、さまざまな悪因を集起させたことによって現れたものである。という真理、またはこの真理を悟ることを言う。 集諦とは「苦の源」、現実に苦があらわれる過去の煩悩をいうので、苦集諦といわれる。「集」とは招き集める意味で、苦を招きあつめるものが煩悩であるというのである。
この集諦の原語は「サムダヤ」(samudaya)であり、この語は一般的には「生起する」「昇る」という意味であり、次いで「集める」「つみかさねる」などを意味し、さらに「結合する」ことなどを意味する。その点、集の意味は「起源」「原因」「招集」いずれとも解釈できる。
苦集諦とは "duHkha-samudaya-satya" とあるので、「苦の原因である煩悩」「苦を招き集める煩悩」を内容としている。そこで、具体的には貪欲や瞋恚(しんに)、愚痴などの心のけがれをいい、その根本である渇愛(かつあい)をいう。これらは欲望を求めてやまない衝動的感情をいう。
さて、仏教において苦の原因の構造を示して表しているのは、十二縁起である。この十二縁起とは苦の12の原因とその縁を示している。十二縁起より、苦とは12の原因のシステムという事になる。12個集まってそれ全体が苦なのである。だから、「無明」も「渇愛」も、苦の根本原因であり苦集諦である。
滅諦
滅諦(めったい、nirodha-aaryasatya)とは、「苦滅諦」といわれ、煩悩が滅して苦のなくなった涅槃の境地を言い、いっさいの煩悩の繋縛(けばく)から解放された境地なので解脱の世界であり、煩悩の火の吹き消された世界をいう。または、苦の滅があるということを認識すること、すなわち苦の滅の悟り、または苦の滅を悟ることを滅諦という。
具体的には、諸法皆空という言葉で言われているように、森羅万象全ての法、すなわち諸法はすべてこれ空であって、実体のあるものではなく、因と縁から成り立っているものであり、苦は縁であり、縁は因(たとえば心や行いなど)を変えることによって変わりうるという悟りであるとも言える。
道諦
道諦(どうたい、maarga-aaryasatya)とは、「苦滅道諦」で、苦を滅した涅槃を実現する方法、実践修行を言い、これが仏道すなわち仏陀の体得した解脱への道である。その七科三十七道品といわれる修行の中の一つの課程が八正道である。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

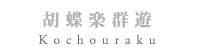




 「怨憎会苦(おんぞう...
「怨憎会苦(おんぞう...